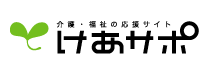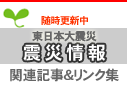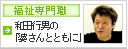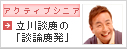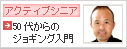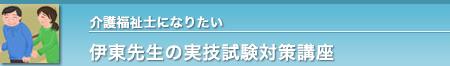
筆記試験が終わると次は実技試験が待っています。試験委員が見守るなかでの実技試験は、緊張してしまってなかなか思いどおりにできないものです。
実技試験の効果的な試験対策は? 評価のポイントは? 試験直前には何をしたらよい?
伊東利洋先生が、第26回介護福祉士実技試験に向けて4回にわたって講義します。
実技試験の効果的な試験対策は? 評価のポイントは? 試験直前には何をしたらよい?
伊東利洋先生が、第26回介護福祉士実技試験に向けて4回にわたって講義します。
第1回 出題基準・合格基準を理解しよう!
介護福祉士筆記試験、お疲れさまでした。次は3月2日(日)に実技試験が控えていますね。
実技試験も筆記試験と同様、「何が」「どのように出題されて」「どのくらい得点すると合格するか?」「今年は何が出題されそうか?」など、過去の傾向などを踏まえた「受験対策」をとることが重要です。
「受験」と「実務」との違いなどにも留意しながら、しっかりと対策をとっていきましょう!
出題基準を理解しよう!
実技試験は、「出題基準」(試験委員が試験課題を作成するための基準)に基づいて作成されます。
この基準を理解することは、何が「採点」されるポイントかを理解する上で非常に大切ですので、概要をつかんでおきましょう。
この基準を理解することは、何が「採点」されるポイントかを理解する上で非常に大切ですので、概要をつかんでおきましょう。
出題基準
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護の原則 | 安全・安楽 | 転落・転倒・強打の防止 |
| 麻痺側の保護 | |||
| 誤嚥の予防 | |||
| 自立支援 | 残存機能の活用 | ||
| 意欲の促進 | |||
| 個人の尊厳 | コミュニケーション | ||
| 事前の説明と承諾 | |||
| 自己決定 | |||
| 接遇(言葉遣い・態度) | |||
| 2 | 健康状況の把握 | 利用者の健康状況の把握 | 外見(観)の変化を察知する観察 |
| 意識(反応)状況の変化を察知する能力 | |||
| 体温、脈拍、呼吸の測定 | |||
| 介護者の健康管理 | ボディメカニトクス | ||
| 感染予防 | |||
| 3 | 環境整備 | 室内環境 | 換気 |
| 温度、湿度 | |||
| 冷暖房 | |||
| 清潔 | |||
| 採光 | |||
| ベッド | ベッドの機能 | ||
| ベッドメイキング、リネン交換 | |||
| 4 | 身体介護 | 体位と体位変換 | 体位の種類 |
| 体位(身体)の保持と膝折れ防止 | |||
| テコの原理、ボディメカニクスの活用 | |||
| 体位の変換 | |||
| 移乗動作 | 車いす | ||
| ポータブルトイレ | |||
| ストレッチャー | |||
| いす | |||
| 移動・歩行介助 | ベッド上での移動 | ||
| 車いす、ストレッチャーでの移動 | |||
| 肢体不自由者の歩行介助 | |||
| 視覚障害者の歩行介助 | |||
| 食事の介助 | 食事の種類と介助 | ||
| 食前の介助 | |||
| 摂食の介助 | |||
| 食後の介助 | |||
| 排泄の介助 | トイレ及びポータブルトイレへの誘導と介助 | ||
| 便器・尿器の介助 | |||
| おむつの介助 | |||
| 保清の介助 | 清拭 | ||
| 入浴・シャワー浴 | |||
| 足浴・手浴 | |||
| 洗面 | |||
| 口腔ケア・義歯の取り扱い | |||
| 洗髪 | |||
| 衣服の着脱 | 衣服の着脱 | ||
| 寝衣の交換 | |||
| 衣服のたたみ方 | |||
| 整容の介助 | 髪をとかす | ||
| ひげそり |
出題基準で特に重要な点は、「1 介護の原則」「2 健康状況の把握」を適切に表現することだと言われています。それを踏まえて、「4 身体介護」を課題にそって展開していきます。
合格基準を理解しよう!
出題基準に沿って課題が出題され、各課題の「チェック項目」をクリアすると得点になります。
「合格」するには、「合格基準」を満たさなければなりません。何点くらいで合格するのかを確認しておきましょう!
「合格」するには、「合格基準」を満たさなければなりません。何点くらいで合格するのかを確認しておきましょう!
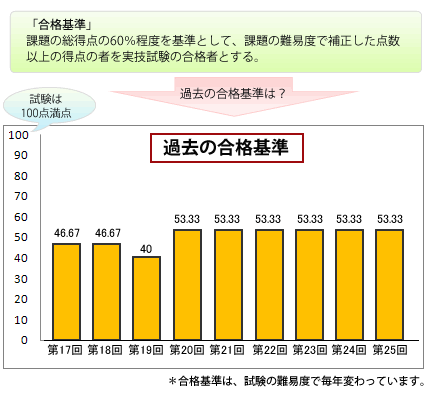
過去の合格基準を眺めてみますと、課題の難易度で前後しているようですが、近年は100点満点中、「約54点」の得点で合格していることがわかります。
また、複雑な課題であれば、40点〜50点でも合格できるようですね。
また、複雑な課題であれば、40点〜50点でも合格できるようですね。
実技試験の最大の敵は、「緊張」だと言われています。
「緊張」のあまり、「何をしたか覚えていない・・・」というのが、多くの不合格者の共通点です。「緊張」の原因の一つに、「完璧」にしなければ合格できない・・・という思い込みがあります。
まずは、「半分程度」の課題クリアで合格できる! と心のハードルを下げることが大切です。
「緊張」のあまり、「何をしたか覚えていない・・・」というのが、多くの不合格者の共通点です。「緊張」の原因の一つに、「完璧」にしなければ合格できない・・・という思い込みがあります。
まずは、「半分程度」の課題クリアで合格できる! と心のハードルを下げることが大切です。