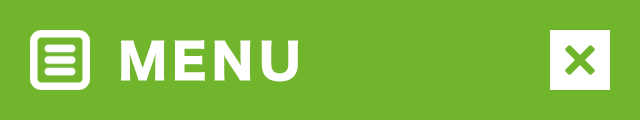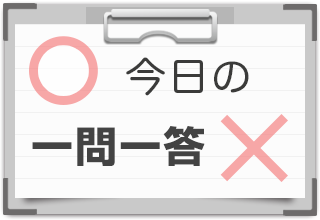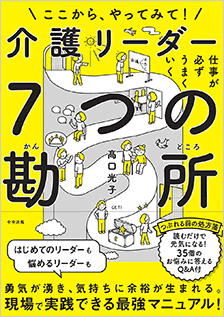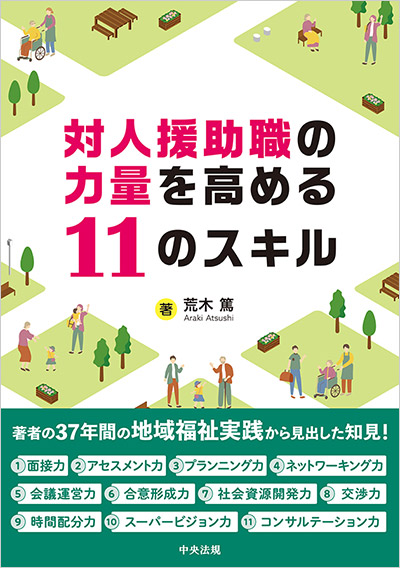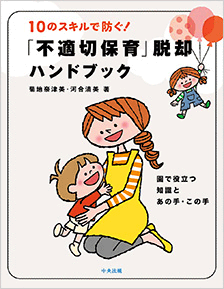精神保健福祉士になるには
精神保健福祉士になるには
精神保健福祉士は、精神的な障害のある人の相談に応じ、生活にかかわるさまざまな支援を行う国家資格の専門職です。
精神保健福祉士とは?
精神保健福祉士は、心に病を抱えた人がスムーズに生活を営めるように、日常生活や社会参加に関する相談に応じ、助言や必要な訓練、環境調整などを行う専門職です。1997年の「精神保健福祉士法」施行に伴って誕生し、2005年の「障害者自立支援法」の制定、2012年の「障害者総合支援法」の制定を受けて、医療・保健・福祉にまたがる専門職として活躍の場が広がっています。
仕事の内容は?
精神保健福祉士の仕事は、精神的な障害のある人の生活を支えることです。精神科病院では入院から退院までの相談に応じ、退院後の生活を送るためのさまざまな支援を行います。また、家族や関係機関との連絡調整を行い、社会参加など暮らしに広がりがもてるように支援します。地域では、相談支援や生活訓練、就労支援などに取り組みます。また、精神保健福祉センターや保健所などの行政機関で住民のメンタルヘルス啓発活動にも携わります。
精神科デイケアで働く精神保健福祉士の「ある一日」

【08:30】 出勤
他のスタッフとの申し送りや一日のスケジュールを確認する。
【09:30】 デイケアを利用するメンバーの出迎え
あいさつをしながら表情や身なりを観察し、コンディションの把握に努める。朝のミーティングで出欠や今日のプログラムの確認をした後、全員で体操をして体をほぐす。
【10:00】 午前のプログラムを開始――ミーティング
今日は週に1回、メンバーとスタッフが野外活動や院内イベント、デイケアプログラムなどに関して意見を交換し合うミーティングを行う日である。この目的は、社会性の獲得(集団の一員という意識をもつ)、メンバーの主体性の尊重(自分たちでプログラムを検討する)、話し合いを通じた協調性の訓練、集団のなかで自己主張する訓練などである。精神保健福祉士は、これらの目的が達成されるよう、メンバーに声かけなど適宜働きかける。同時に、一人ひとりの様子を見ながら心身のコンディションにも目配りをする。
【11:30】 メンバーの昼食
メンバーの持ち回りによる給食当番がいて、スタッフは配膳やお茶配りを手伝う。
【12:00】 昼休み
持参したお弁当を食べながらスタッフルームで過ごす。朝のミーティングや午前のプログラムで気になったメンバーの情報をスタッフ間で共有する。
【13:00】 午後のプログラムの準備
今日はゲームをするので、将棋盤やトランプ、オセロ、ボードゲームなどをメンバーと一緒に机に並べる。ゲームを行う目的には、メンバーの体験の幅を広げる、ゲームを通してメンバー間のコミュニケーションを促進する、ゲームに参加することで頭や手先を使う、ルールに則った正しい遊び方を学ぶ、勝ち負けを通して自分の感情を表現する、不満や葛藤を受け入れるなかで感情のコントロールのしかたを学ぶ、などがある。
【13:30】 ゲームスタート
ゲームを始める。プログラムを行う際には、メンバーにいつもと違った様子はないか観察し、会話のなかでは困りごとの相談にものる。また、各メンバーの対人関係能力の向上のため、メンバー同士の交流に介入することもある。こうしたプログラム中の様子から、メンバー個々の能力や性格、それまでの生活経験等をアセスメントし、支援のニーズを把握していく。
【15:00】 プログラム終了
メンバーと一緒に掃除をする。掃除を行うなかで掃除のしかたを学び(生活能力の向上)、役割意識や協調性を養い、責任を果たすことを学習できる。精神保健福祉士は、そのような意識をもって声かけ等を行う。
【15:30】 帰りのミーティング
メンバー一人ひとりが今日の感想を話す。精神保健福祉士は、それぞれのメンバーにとって一日がどうであったかをしっかりと聞き、プログラム中に行った自らのアセスメントとすり合わせを行う。次回以降もメンバーに目的意識をもって来てもらうために、今日のプログラムで得たこと、よかったこと、学んだことなどを意識的に話してもらう。ゲームに負けて落ち込んでいるメンバーには、「でも、あそこの一手はよかったですよ」などとフォローする。
【16:00】 スタッフ同士の話し合い
帰宅するメンバーを見送った後、各職種の専門性にもとづくメンバー一人ひとりについてのアセスメントを話し合い、その情報を共有し、今後の支援方針を確認する。その後、メンバーの個人記録や活動記録を作成する。その他、関係機関への連絡、主治医や院内の他職種と情報交換、最近休みがちなメンバーへの電話連絡などを行う。
【17:30】 退勤
地域で有志の精神保健福祉士が集まり定期的に開催しているグループスーパービジョンに参加。その後、帰宅。
どんな人を対象に、どんなところで働くの?
<対象>
精神障害のある人、メンタルヘルスの課題をかかえる人、およびその家族など
<職場>
医療機関(精神科病院・診療所、総合病院精神科)、生活支援にかかわる機関(相談支援事業所、地域活動支援センター、グループホーム、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型、B型)、自立訓練事業所、救護施設、児童養護施設等)、行政機関(自治体・保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター)、司法施設(保護観察所等、矯正施設)、その他(社会福祉協議会、ハローワーク、介護保険関連施設、教育機関、企業)など
資格を取るまでの道のりは?
精神保健福祉士の資格を得るためには、「精神保健福祉士国家試験」に合格しなければなりません。国家試験を受けるまでには11の道のりがあり、大きくは大学等で指定科目を履修する、短大等で指定科目を履修して実務1~2年を経験する、養成施設を経るという3つのルートに分けられます。

- (注意1) 「短期養成施設」「一般養成施設」(以下、「養成施設等」という。)の入学に必要な学歴・相談援助実務等は、各「養成施設等」において審査・決定を行ないますので、ご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
また、「実習科目免除」の可否につきましてもご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。 - (注意2) 「5年以上の実務経験者で、厚生労働大臣が指定した講習会を修了したもの」(法附則第2条)で受験資格を取得した者が試験を受けることができるのは、平成15年3月31日(第5回試験)までです。
平成15年4月1日(第6回)以降の試験は受けることができません。
受験資格の詳細は、こちらを参照ください。
精神保健福祉士国家試験について
国家試験は、年1回行われます。試験の形式は、筆記試験です。
試験科目
筆記試験科目は、次の17科目です。なお、1~11までの11科目については、社会福祉士との共通科目となっています。
- 1. 人体の構造と機能及び疾病
- 2. 心理学理論と心理的支援
- 3. 社会理論と社会システム
- 4. 現代社会と福祉
- 5. 地域福祉の理論と方法
- 6. 社会保障
- 7. 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 8. 福祉行財政と福祉計画
- 9. 保健医療サービス
- 10. 権利擁護と成年後見制度
- 11. 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 12. 精神疾患とその治療
- 13. 精神保健の課題と支援
- 14. 精神保健福祉・相談援助の基盤
- 15. 精神保健福祉の理論と相談援助の展開
- 16. 精神保健福祉に関する制度とサービス
- 17. 精神障害者の生活支援システム
第25回(令和4年度)受験データ(厚生労働省発表)
受験者数/7,024人
合格者数/4,996人
合格率/71.1%
出題基準・合格基準については、こちらをご参照ください。
資格取得等に関する問い合わせ先
【公益財団法人 社会福祉振興・試験センター】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-6 SEMPOSビル
国家試験情報専用電話 TEL 03-3486-7559