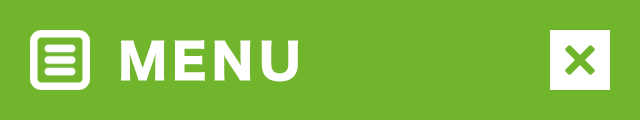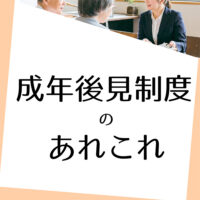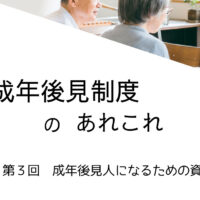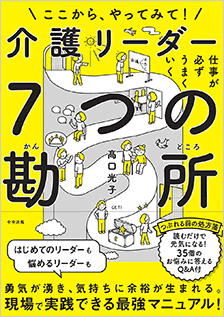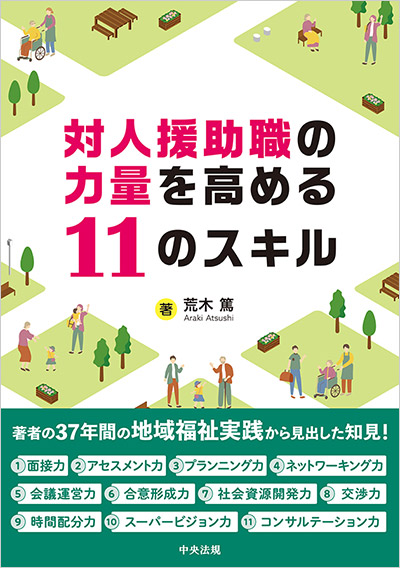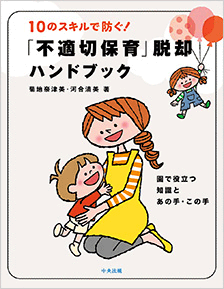成年後見制度のあれこれ
第2回 成年後見の種類と役割
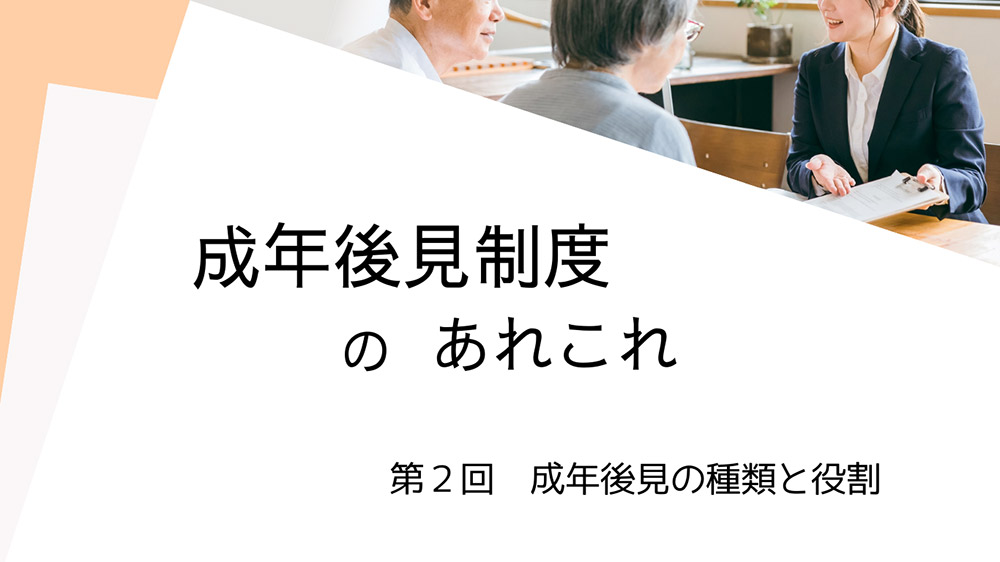
【著者】
君和田 豊(きみわだ ゆたか)
君和田成年後見事務所代表、社会福祉士・精神保健福祉士・社会保険労務士・旧:訪問介護員(ホームヘルパー)1級
2007(平成19)年に社会福祉士登録。2012(平成24)年に現:公益社団法人日本社会福祉士会の成年後見人養成研修修了後、一般社団法人千葉県社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」の登録員として活動中(後見人等の候補者として千葉家庭裁判所に名簿登録)。
皆さんは「成年後見人の役割」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。
教科書的な法的役割としては「財産管理」と「身上監護」となっていますが、では実践レベルではどうでしょうか? 介護保険や各種福祉サービスの手続きは当然のこととして、ホームヘルパーばりの食事・買物・ゴミ出し、地域や時期によっては雪かき、はたまた配偶者の納骨に親子ゲンカの仲裁までもと、事実行為のオンパレードではないでしょうか。無論すべての後見人ではなくとも、いわゆる「後見人あるある」を経験された方も多いと思います。
今回はそんな後見人の役割を、後見類型と合わせて見てゆきます。
後見、保佐、補助の違い
まず教科書的な定義ですが、法定後見の類型には対象となる方の状態に応じて次の3種類があります。
・後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の人
・保佐…判断能力が著しく不十分な人
・補助…判断能力が不十分な人
類型によって、代理・同意・取消など後見人等の行うことのできる法律行為の範囲が定められています。
では果たして、それぞれの違いを明確に定義できるものでしょうか?
類型の違いはどこから?
例えば、筆者が受任していた後見類型の認知症高齢者に、Aさんという方がいました。
Aさんは戦前の台湾生まれでした。終戦時は軍属であったことから、どうやら初対面から後見人(筆者)のことを軍が派遣した部下だと思っていたようで、色々と命令されたものです。その命令内容は「(好物の)羊羹買ってこい」や「背中が痒いのでかけ」などで、会話は困難でしたが意志表明としては理解できました。ただ確かに不適応行動は多く、申立の診断書では「自己の財産を管理・処分することができない(=後見相当)」にチェックが入っていました。
また、保佐類型のBさんは、知的障害はあるものの軽く(療育手帳Bの2)、上場企業の特例子会社で障害者雇用されており、週5日/37.5時間のフルタイム勤務で働いていました。仕事の面でも評判がよく、無遅刻無欠勤で表彰されるほどでした。障害基礎年金と合わせて月の収入が手取りで20万円近くとなり、社会福祉法人の運営するグループホームに居住していたので、家賃も特定障害者特別給付費もあり、大変お安く済んでいました。
このお二人に共通するのは、法律上、後見も保佐も定義はありますが、それぞれの当事者の状態は一義的に定義できるものではない、ということです。
Aさんの場合、要介護認定が3でした。認知症の度合いからすると「そこまで重くないのでは……」と感じましたが、申立時の診断書を長谷川式の点数なども合わせて見てみると、かなり重度という診断でした。私の考えすぎかもしれませんが、診断が重い方が後々福祉サービスの利用などで有利になるということで、そのような診断書になったのではないかと思ったりもします。実際、Aさんは特別養護老人ホームに入居しましたが、2015(平成27)年4月以降、特別養護老人ホームの入居対象は要介護3以上です。これも「後見制度あるある」かもしれません。
またBさんですが、40歳過ぎまで何らの福祉的支援を受けず、一般就労で生活していました。ただ金銭的管理ができず、また給与をもらってもあっという間に浪費してしまうため、消費者金融からの借入で賄っていたところ返済に行き詰まり、破産申立に至る手前で、今の福祉的支援につながれた方です。
筆者が直接かかわってはいないのですが、Bさんは社会福祉法人の支援を受けてから療育手帳の取得と、障害基礎年金2級を受給しています。筆者は社会保険労務士として障害年金の申請業務を行うこともあり、障害年金の受給についてはある程度熟知しているつもりですが、診断基準に照らすとBさんの知的障害の程度ではおそらく不支給になるのではないか、と受任当初は不思議に思っていました(なお、今でもBさんは保佐類型ではなく補助類型相当だと思っています)。
受給後の障害年金証書を見ると、やはり次回の更新判定の有効期限がありました(=永久判定ではない)。そこで受任時に社会福祉法人の支援員の方に次回以降における障害基礎年金の診断書の心配をお聞きしたところ、「ウチの頼んでいる先生なら(障害を)重く記載してくれるので大丈夫」という回答でした。
また別の後見類型の方では、脳性麻痺による重度障害で、5歳の頃から何十年も重症心身障害病棟に入院中の方もおられます。こちらの方の場合は、確かに後見相当だなとは思います。
診断が必ずしも正確に行われていないという問題はありますが、「後見」「保佐」「補助」と、家庭裁判所への申立や審判の書類を見ても、実際にご本人にお会いしてみないとその状態は全くわからないものだということを、日々の後見実務の中で本当に実感しています。
後見人の役割
後見人は「便利屋」ではない?
ここまで書いた通り、後見人はあくまでも「法的な役割」を担う存在です。例えば被後見人の方が有料老人ホームやグループホームなどに入居している場合、入居費用、その他の諸費用などを被後見人に代わって支払いを行います。
しかしその役割内容の線引きは難しく、近くに被後見人の親族などがいない場合(被後見人等は、身寄りがないか、親族がいても疎遠な場合が多いです)、病院の送り迎え(診察時の付添含む)や介助、日用品の買い物などを行うケースもそう珍しいことではありません。休みの日に「すみません、ちょっと被後見人さんの着替えの換えを持ってきてくれませんか」なんて電話も日常茶飯事です。本来なら後見人の役割ではないところでも、やはり日常生活の面倒を見てしまうのが実際の後見人です。
親族のいない場合の死後事務
また第9回で詳しく触れる予定ですが、死後事務の問題もあります。被後見人が亡くなった場合は成年後見人の業務もそこで終了しますが、実際には葬儀まで執り行います。死後事務とは通常ご遺体の引き取り、死亡届の提出、火葬までですが、親族がいない場合は、後見人がそのすべてを一人で執り行うことになります。ご遺骨についても対応を迫られます。
やはり被後見人になられる方は高齢の方がほとんどなので、他の後見人の話を聞いていても、月に複数回の葬儀を執り行うことも珍しくありません。仕事とは言え、やはり人の死に立ち会うのは辛いものです。少なくとも筆者の経験上は、親族がいて本人の財産使って葬祭まで行うような方は少なく、直葬(死亡診断が出て、24時間が経ち、直接火葬すること)がほとんどです。参列者の誰もいない火葬が終わり骨上げをすることは、一人の人間としても、また人生の最後までご本人様の支援を続けてきた身としても、本当に心が痛みます。
後見人はただ法的な役割を担うだけでなく、財産管理及び身上監護を達成するため、考えられかつ可能な活動には全て取り組み、被後見人のよき理解者、そして人生の伴走者であると思って仕事を続けています。