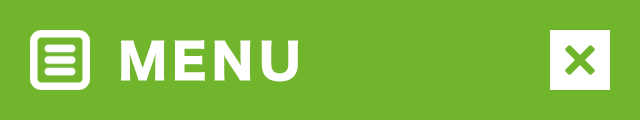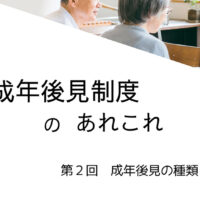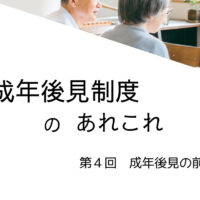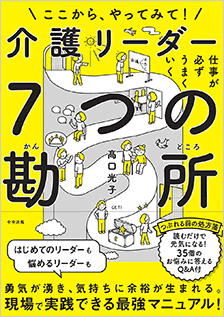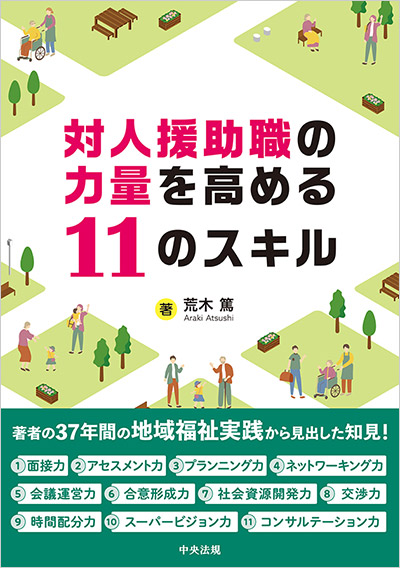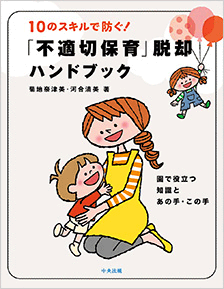成年後見制度のあれこれ
第3回 成年後見人になるための資格と要件
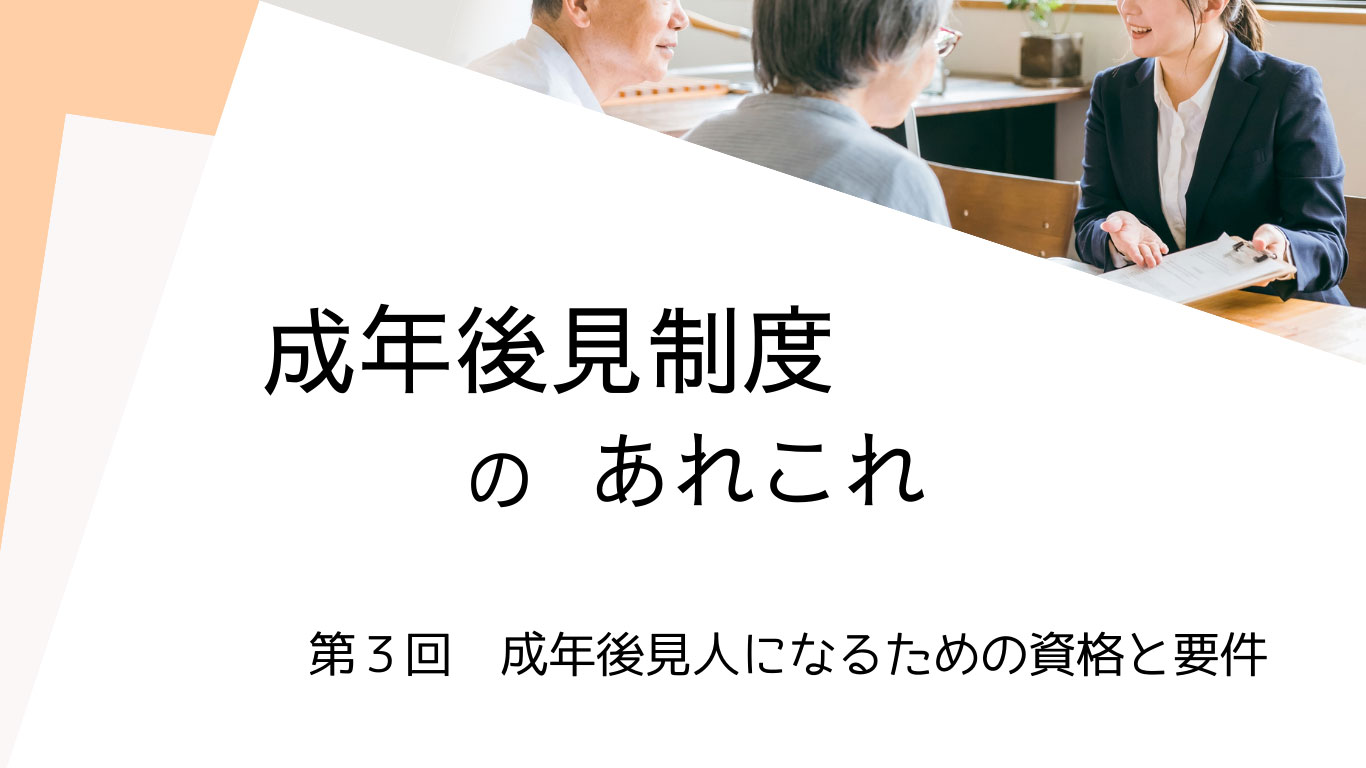
【著者】
君和田 豊(きみわだ ゆたか)
君和田成年後見事務所代表、社会福祉士・精神保健福祉士・社会保険労務士・旧:訪問介護員(ホームヘルパー)1級
2007(平成19)年に社会福祉士登録。2012(平成24)年に現:公益社団法人日本社会福祉士会の成年後見人養成研修修了後、一般社団法人千葉県社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」の登録員として活動中(後見人等の候補者として千葉家庭裁判所に名簿登録)。
3月に入り、日毎に春らしくなってまいりました。被後見人の方々も冬場は体調を崩したり、またこもりがちにもなりますが、これからは暖かい日差しに誘われ、散歩に出かけるなどの外出も増えてくるでしょう。
以前そんなとある春の時期に、認知症高齢者である被後見人のAさんと面会した際、外出の機会をとレクリエーション(お花見)への参加をお声掛けしたことがありました。それなりに促してみましたが、日程を確認してもAさんは黙り込んでしまうばかり。その時「きっと意味が分からないんだ」と考え、Aさんに聞くことをやめてしまいました……、というようでは成年後見人失格ですね。
このように成年後見制度において本人の意思尊重の視点が十分でないという課題が指摘されてきたことから、近年ですがガイドラインが出来ました。後見人としてAさんの思いに、「どう考えるか(黙っている意味は? 話しやすい環境か? 等)」、そして「どう動くか(意思を表明しやすい工夫やサポート等)」。このように本人の意思決定支援を踏まえた後見を行うことが、成年後見人の資質として必要です。
今回はそのような成年後見人の資格と要件について見てゆきたいと思います。
成年後見人の選任基準
後見人については、民法第843条第4項に成年後見人の選任が記載されています。この条文に基づき、「家庭裁判所が適任と審判した者」が選任されるわけですが、最終的には裁判官の独任での判断となります。このため行政通達のような明確な基準ではないですが、選任基準としては被後見人の状況や家庭環境など、さまざまな要素が考慮されます。以下は主な選任基準(とされるもの)です。
① 本人及び家族の意向
② 候補者の職業・専門性
③ 経済的信用力・倫理性
④ 後見人候補者と被後見人の関係性
⑤ 成年後見制度の利用目的と必要性
⑥ 後見人の負担と継続性
至極当然の内容ばかりですが、第1回の成年後見人等と本人との関係でみた通り、まず親族は後見人に選ばれることは少なく、全体としては専門職が後見人に選ばれています。
これは制度において被後見人等の財産保全の観点が重視された結果です。つまり、成年後見制度当初から親族として「本人の子」が選任される場合が多く、結果として財産管理が不十分だった(親の財産はいずれ自分が相続するものだとして、自分のもののように使うなど)ことから、専門職後見人が多く選ばれるようになってきたのです。
また民法には、後見人等になることのできない要件(欠格事由)が規定されています(民法第847条)。
① 未成年者
② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③ 破産者
④ 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤ 行方の知れない者
こちらも至極当然の内容ばかりですね。これらの欠格事由に該当しなければ、選任基準を総合的に考慮し、後見人等として適格な者が審判されます。
成年後見人はどうやって選任されるか
第10回で審判申立書にふれますが、「後見・保佐・補助開始等申立書」には、「成年後見人等候補者」の欄があります(参考)。
誰を後見人等に選任するかは裁判所の判断事項ですので、後見人等の候補者を掲げて申立を行った場合であっても、その通り選任されない場合もあります。
親族による申立は減少傾向
ではここに親族の方を記載したら、選任されるでしょうか?
先ほど書いた通り、後見人には専門職が多く選ばれるようになってきています。しかし、2019(平成31年)年に最高裁判所は「後見人等の選任の基本的な考え方」を改め、親族が後見人となることが望ましいという見解を発表しました。
最高裁と専門職団体との間で共有した後見人等の選任の基本的な考え方
- ◯本人の利益保護の観点からは,後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は,これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい
- ◯中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は,専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討
- ◯後見人選任後も,後見人の選任形態等を定期的に見直し,状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う
ですので、親族が候補者となり、選任基準に照らして問題がない場合は、原則として親族が後見人に選任されます。
しかし、申立書を提出するということは、親族の場合は裁判所の事前説明会等に参加し、選任要件の説明を受けています。ここは裁判所の内部事情ですが、被後見人等の預貯金等の流動資産額が一定程度ある場合(裁判所によって異なり500万円~1200万程度)には、親族ではなく原則として専門職後見人を選任する(あるいは成年後見監督人の選任や、成年後見制度支援信託・成年後見制度支援預貯金の利用する)という方針が出ています。これを知れば、親族については最初から申立そのものをしないことも考えられます。親族後見人の減少は、この内部事情の影響が大きいと思います。
状況に応じた専門職が選任される
では専門職の場合はどうでしょうか?
後見人を受任する主な専門職としては、弁護士・司法書士・社会福祉士などが挙げられます。まず、「身上監護が主な目的」(≒福祉的支援が必要)な方の場合は、確実に社会福祉士が選任されます。というのも、福祉的支援が必要な方は財産がない・少ない場合が多いため、財産管理に適した専門職を選任する必要性が薄いためです(特に生活保護受給者は、ほぼ100%社会福祉士ではないかと思います)。
逆に、弁護士や司法書士は「財産管理が主な目的」または「財産と身上監護の両方が目的」のケースで選任されることになりますが、特に何億・何十億という多額の資産をもつ場合や、訴訟案件がある場合は弁護士になるでしょう。司法書士は弁護士と社会福祉士の中間ということになると思います。
専門職の選任は専門職団体への入会がほぼ必須
実は専門職の選任の場合、その管轄裁判所に後見人等の候補者として名簿登録されているかで選任が大きく異なります。
この名簿登録の仕組みですが、3職種のいずれも、所属する専門職団体からの推薦者です。各団体とも研修等を通じて成年後見人等として適格と判断した会員を裁判所に候補者として提出しているので、裁判所としては、必ず推薦された候補者を後見人として選任します。受任したい専門職にとっては、大変ありがたい制度です。
先の「後見・保佐・補助開始等申立書」で候補者欄が「裁判所に一任」という形で提出されると、裁判所は専門職団体に候補者の推薦依頼を行い、推薦された専門職を後見人等として選任することとなります。
弁護士や司法書士であれば専門職団体への入会は強制ですが、社会福祉士は任意です。実は社会福祉士の場合、社会福祉士会に所属せず独立して活動する(審判される)こともあると思いますが、別の団体等で名簿登録されているか、あるいはよほど適格であると裁判所に認められなければ審判されません(実態としては個人では不可能です)。成年後見人として活動する、あるいは将来活動を考えている方は、やはり社会福祉士会への入会をお勧め致します。
なお、名簿登録は管轄裁判所ごと、つまり都道府県単位で行われます。例えば筆者の場合、千葉県の名簿に登録されているので、千葉県では本庁は無論、どの裁判所の支部・出張所でも選任されますが、他の地方自治体の裁判所では名簿登録されていないので、同じようなことにはなりません。
このため、例えば隣接する自治体の方で、個人的に後見人等の依頼(就任の打診)があっても、当方としては事情を説明して辞退させていただいております。居住地が離れていれば、確かに財産管理や身上監護面で被後見人のためにはならないと思いますが、場所によっては可能なことも十分にあります。せっかく自分にお話しいただいたことをお断りするのは事情があるとはいえ歯がゆいことで、将来的には見直されることがあればと個人的には思っています。
最後にですが、社会福祉士会は毎年2月が全登録員の定期報告(年1回)の時期となっています。このためこれから2025年2月の受任状況が公表されますが、今のところ2024年2月が最新です。興味があればぜひこちらもぜひ参照してみてください。