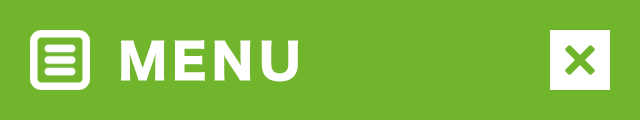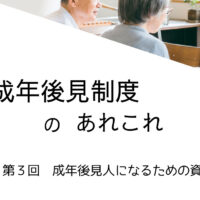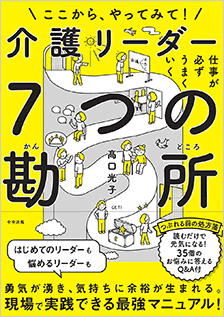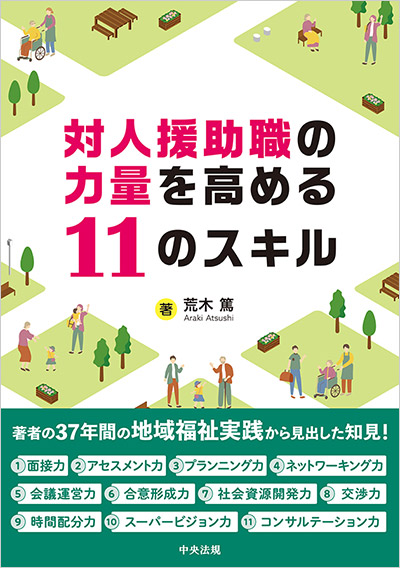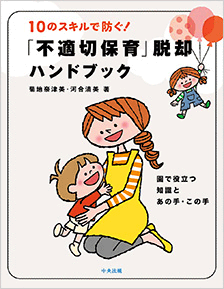成年後見制度のあれこれ
第4回 成年後見の前提知識
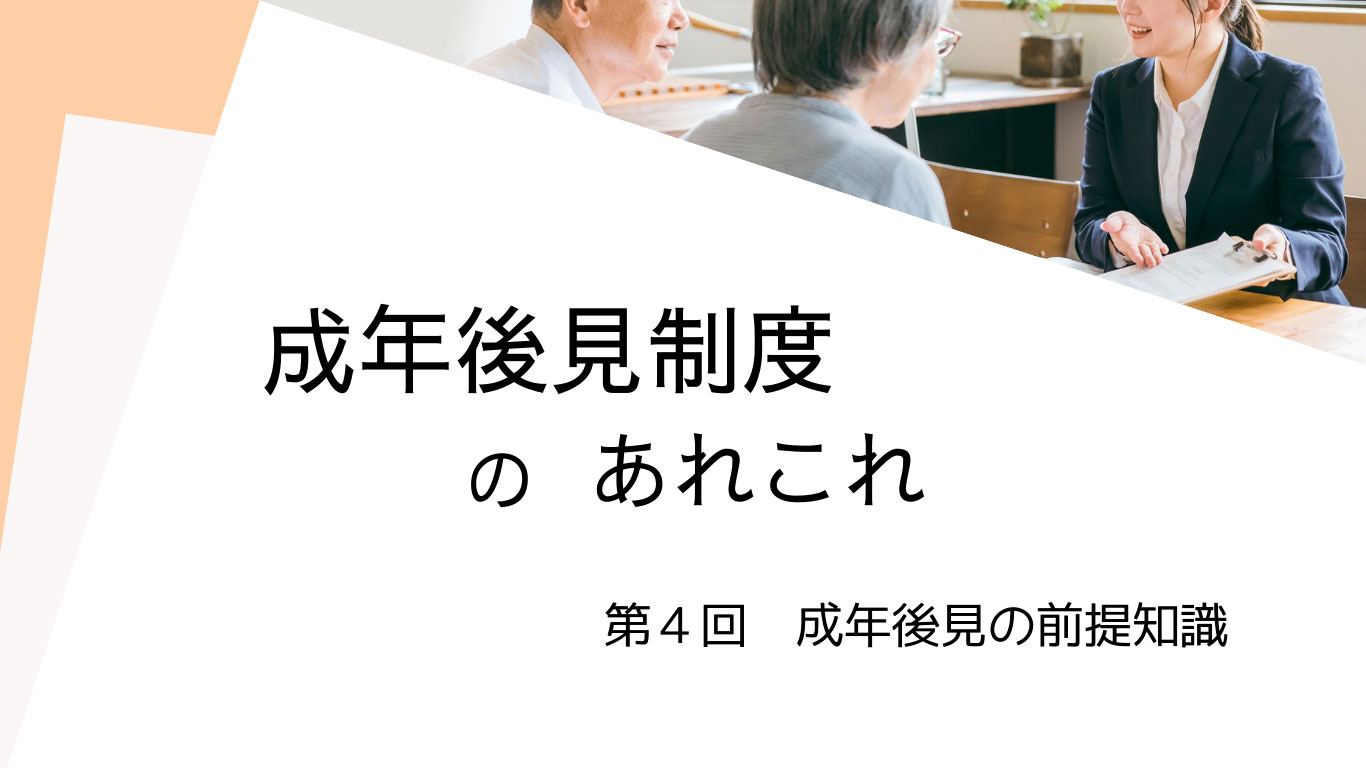
【著者】
君和田 豊(きみわだ ゆたか)
君和田成年後見事務所代表、社会福祉士・精神保健福祉士・社会保険労務士・旧:訪問介護員(ホームヘルパー)1級
2007(平成19)年に社会福祉士登録。2012(平成24)年に現:公益社団法人日本社会福祉士会の成年後見人養成研修修了後、一般社団法人千葉県社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」の登録員として活動中(後見人等の候補者として千葉家庭裁判所に名簿登録)。
2000(平成12)年、介護保険制度と同じ年に成年後見制度が始まってから、今年で25年になります。
社会福祉基礎構造改革によって地域福祉中心となってからの四半世紀、皆さんはどのように感じているでしょうか。実は筆者はちょうど2000(平成12)年から福祉業界で働きはじめたのですが、それから今までの変化を鑑みて、今は本当に独居高齢者の方が増えたなと感じています(国民生活基礎調査の結果からも明らかですが……)。
社会福祉基礎構造改革で制度の両輪と言われたのが、介護保険と成年後見制度です。「措置から契約へ」となった福祉制度。では契約を結ぶ意思能力が不十分となった独居高齢者の方は……。
今回はその成年後見の前提知識をみてゆきます。
民法による成年後見制度
民法は、個人と個人が関わる私人間(しじんかん)関係を定めた法律です。主に財産関係(財産法)や家族関係(親族法)についてのルールを定めていますが、パンデクテン方式という「共通のルールを前に出す」という整理の仕方で構成されており、その前提が「契約」です。
契約の成立に必要なものはなんでしょうか? 民法では、すべての人が「権利能力」を持ち、出生と同時に権利義務の主体となります。しかし、「意思能力」(自分の行為の結果を理解する能力)や「行為能力」(単独で有効な法律行為をする能力)には個人差があります。
行為能力が制限される人には保護制度が設けられていて、制限のある方が契約をするためには、本人のために代わって契約をする代理人が必要です。かつて地縁血縁が強かった時代は遠方の身内やあるいは知人がその代わりをしてくれていましたが、2000年ごろにはそれも限界を迎えていました。
そうすると独居高齢者の場合、意思能力が不十分となり契約を結ぶ能力が低下または失われたときは、1人で暮らすことができなくなってしまいます。そういった状況に社会全体で対応するため、成年後見制度が始まりました(介護保険制度も同じような経緯です)。このとき法律の規定によって定められた代理人が、法定代理人である親権者や未成年後見人、成年後見人などとなります。
余談ですが、ちょうど介護保険制度が開始される半年前、1999(平成11)年10月から利用申請が始まり、初日から市町村の窓口が全国で混雑したというニュースを今でも覚えています。介護保険の認定は申請から30日以内と法律で規定されていますが、申請からその後もかなりの時間がかかり、制度開始まで様々な報道もされました。同時に始まる成年後見制度は、その陰に隠れてでしょうか、あまりニュースにならなかったようでしたが……。
地域福祉と共生社会
「措置から契約へ」の福祉制度の転換は、「援助者中心」から「利用者中心」の福祉サービスへの移行とイコールです。
社会福祉事業法が社会福祉法となり、「地域福祉」として、高齢者・障害者・生活困窮者などの支援を必要とする人々が地域で安心して暮らせるよう、住民・行政・専門職が協力して支援体制を整えることとなりました。
また、「共生社会」として、年齢・障害の有無・国籍・性別・経済状況などに関わらず、すべての人が相互に支え合いながら共に生きる社会の実現を目指しています。
介護保険で独居高齢者の在宅見取りも可能に
この結果、認知症があっても1人で暮らして行ける高齢者の方が本当に増えたと思います。2000(平成12)年以前は独居高齢者の方を自宅で看取るのはかなり珍しいことだったと記憶していますが、今は往診医・訪問看護・訪問介護の3点セットがあれば、自宅での看取りも可能となっています。これはやはり介護保険制度のおかげでしょう。制度開始当初はまだまだとは思いましたが、25年経って現場も経験を積み、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院など、医療も充実してきました。独居高齢者の方の在宅看取りは当たり前になってきていますし、それ自体はよいことです。
成年後見の現状
ただ、身寄りのない方への支援はどうでしょうか? 地縁血縁が薄れ、成年後見制度の充実が叫ばれる中、25年経ってもその拡充はまだまだと言わざるを得ません。
「後見人あるある」でも取り上げましたが、独居の被後見人の方が入院すると(全ての後見人ではありませんが)着替えなどを後見人が届けることは多々あります。病院側も簡単に「後見人さん、着替えを持ってきて」と言ったりします。後見人の専門性とは全く関係ありません。
後見人は法律行為をするのが役割ですが、では事実行為は誰が行うのでしょうか? それを誰か探して契約するのが後見人の仕事なのですが、実際には難しく、現時点では後見人が事実行為も行うことが当たり前になっています。そして、どうもそのような後見人が「よい」後見人なのだと周囲からは思われているようです(後見人=家族と同様)。このような現状は、望ましいとは言えないでしょう。ただ誰かが必ずやらなければならないことを、他に誰もできる人がいない以上、後見人が行っているだけのことです。
社会福祉士会では、後見人は最低毎月1回、被後見人の方の自宅を訪問するのがルールになっています。電話やメールがあっても、対面での訪問は被後見人の方にとってこれほど心強いものもないでしょう。筆者も面会のために訪問すると「本当によく来てくれた」と言われますが、面会の際には世間話は無論、「エアコンの使い方を教えてくれ」「テレビが壊れた」「役所の書類を見てくれ」など色々と頼みごとをされます。
特にこのような「身上監護」面の活動が、成年後見制度そのものでも評価されていないということで、2025(令和7)年4月から裁判所の報告様式が大きく変わります。このような点では着実な進展が見られますので、今は大変でもこれから制度も変わっていくでは、と個人的には期待しています。
それなりに長く成年後見活動をしていて思いますが、介護保険も成年後見も、家族の支援があることで成り立っているのが現状です。本当に身寄りのない方の支援は、実際問題として解決できていません。
地域福祉と共生社会の実現には、行政・専門職・住民が協力し、支え合いの仕組みを作ることが重要です。成年後見制度とも密接に関わるため、今後さらに地域との連携を強化し、すでに包括的な支援を推進することが求められています。地域包括ケアシステムのもと、重層的支援体制整備事業の創設などが行われていますが、ぜひ制度も進んでいってもらいたいと思います。