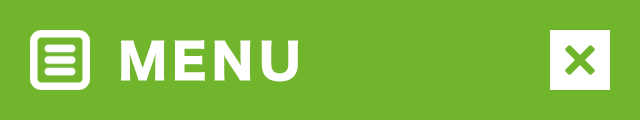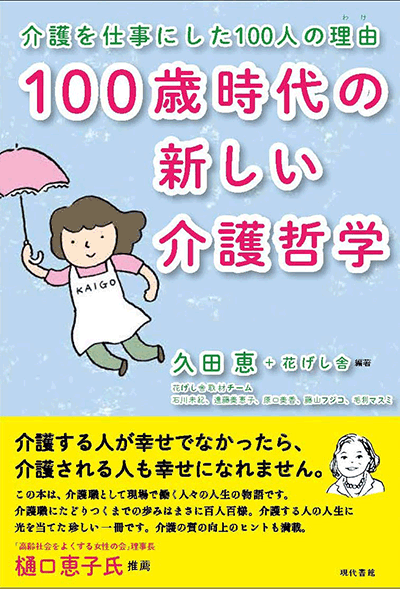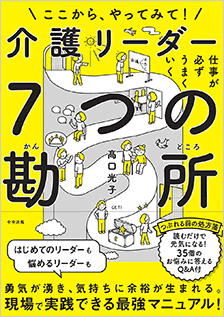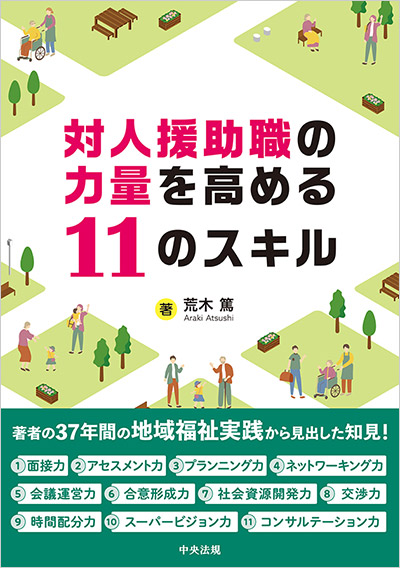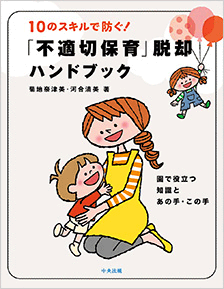福祉の現場で思いをカタチに
~私が起業した理由 ・トライした理由 ~
志をもってチャレンジを続ける方々を、毎月全4回にわたって紹介します!
Vol.78 連載第4回
認知症カフェの活動を続けることは
わたしの使命だと感じています

中島 珠子(なかじま たまこ)さん
コミュニティーナース
2014 年から認知症カフェ「たんぽぽカフェ」、2017 年からは若年性認知症本人と家族の集い「café マリエ」を主催。認知症になっても希望と尊厳をもって暮らし続けることができる社会を創りだす」ことを信念に、認知症のご本人や家族が集い、語らい、仲間づくりや情報交換の場を数多く企画・運営している。
取材・文 毛利マスミ
――前回は、中島さんの若年性認知症への取り組みについてうかがいました。
今回は、渋谷区初の若年性認知症のためのデイサービス設立と今後の活動についてお聞きします。
これまで行政も高齢者認知症に比べて若年性は人数が少ないし、支援の力も入れてなかったんです。ご本人も行くところがないから、家に引きこもっているうちに症状がどんどん進んでいく。家族も仕事を辞めざるを得ない状況になることも少なくありませんでした。
そしてよほど症状がひどくなって、やっと介護保険につながっても、その後には特養(特別養護老人ホーム)しか行くところはありません。これまでは、世間が知らない間に、ひっそりと特養に入っていたんですよね。
それで、caféマリエを続けていくなかで、「若年性認知症の人も、高齢者のデイサービスのような日中にみてもらえる場所がほしいね」ということで、渋谷区との交渉がはじまったんです。人数は少ないかもしれないが、死活問題だと。
当時はわたしも元気だったので、一軒家を借りて自分で開所しようかと考えたくらいです。当事者や家族の訴えに行政が動いてくださり、2019年4月に若年性認知症のデイサービスをオープンできたんです。月曜から土曜まで開所するので、家族は仕事も続けられると、本当に大喜びでした。
全国的にみても、若年性認知症専門のデイサービスはまだまだ少ないんですよ。これは、本当にうれしいできごとでしたが、その後、すぐにコロナ禍になってしまい、デイも稼働できなくなってしまったんです。
その間に、症状が進んでしまった仲間もたくさんいました。若年性認知症の方は、症状が進み家で介護できなくなると、殆どの場合は特養に入所することになります。高齢者にまじって「なつかしい歌を歌いましょう」といわれても、40代の方にとっては全く知らない曲だったりするわけです。周囲は、自分の親よりも年長の方だったり世代が全く違います。
わたしは若年の人たちはとくに、社会と関わることの楽しさを感じてほしいと思っています。体は元気ですし、少しの援助でできることもたくさんあるのですから。
Caféマリエは、いまはケアコミュニティセンターで第4日曜におこなっています。参加は、毎回、スタッフ含めて8人くらいでしょうか。ご本人が来られなくても、家族だけで参加する人もいるんですよ。
若年性認知症のカフェは、区内にはcaféマリエしかないので、絶対にやめられないんです。「月に一度ここに来ることで救われている」と、ご家族からの言葉もいただいています。必要としている人がいる限り、ずっと続いて欲しいと思います。今後は継続についても、引き継いでくださる方を考えていかなくてはなりません。
――2025年1月からは、新しい活動もはじめたとうかがいました。
昨年5月から企画を進めて、2025年1月から動き出した若年性認知症の情報交換の場です。区外も都外もふくめて全国的な活動につなげていきたいと考えています。
「結の碧空(ゆいのあおぞら)」と名づけましたが、澄み渡った一点の曇りもない……というくらい、ここに来たらスッキリして帰っていただきたい、という気持ちを込めました。
これまでもお伝えしていますが、若年性認知症はとにかく情報が少ないんです。行政も若年性の認知症の人がどれくらいらっしゃるのか、どんなことに困っているのか、ご家族の課題は、といったことをあまり把握できていない。
当事者の多くはある日突然、思いもよらぬ病名を告げられ、大きな不安にさいなまれています。65歳未満で発症された方の多くは、就業していたり、子育てをしていたりという現役世代です。病気のことはもちろん、先の見えない暮らしのなかで、どこになにを聞けばいいのかもわからず、家族ともども孤立して、途方に暮れている方が大勢いらっしゃるんです。
わたしがもし、認知症と診断されたら、「仲間がいる」ことが一番心づよく感じると思うんです。どんなに有名な専門医のことばよりも、仲間が「うん、わかる、わかる」という一言に救われる。不安が軽減するんです。
本人には同じ悩みを抱える仲間が必要で、家族同士も交流が大事なんです。
いまは、自ら情報発信をしてらっしゃるご本人さん、ご家族さんもいらっしゃるので、そういう方達ともどんどんつながって、渋谷の若年性認知症の方にも情報を届けたいということで、結・しぶや(渋谷区地域共生サポートサンター)の場を借りて活動をはじめました。わたしの集大成ともいえる活動に育てていきたいと考えています。
すでに、caféマリエで若年性認知症の方のカフェを運営はしておりますが、診断直後のご本人、家族の仲間づくりの場、地域に留まらない活動や情報交換の場としてまずは奇数月の第4土曜日におこなっていきます。暖かくなったら、お弁当持って公園にいこう というようなイベントも地域を超えてやっていきたいと思っています。
――認知症支援をこれまで続けていくなかで、いま、課題に感じていることはなんですか?
やはり後継者を探すことですね。地域にはこだわらずに、思いを同じにする若い人につないでいきたいです。同じ想いで動ける人を探すのは難しいと思いますが、全国に視点を広げれば、それは大勢いらっしゃいます。そういう人の力も借りてやっていきたいですね。
そんな意味でも、結の碧空は、その拠点の一つになると期待しているんです。
じつは、カフェを続けることに疲れてしまった時期もあって、認知症カフェは辞めようかと思ったこともありました。でも、ご家族の方から、「ここに来て話すことでほっとする」「ここで助けられている」というような話があって。一人でも大事にしてくれるのであれば、続けていくべきだって思ったんです。
さらに今年はスターバックスさんのご協力も得て、渋谷のど真ん中で夜カフェもやってみようか、なんて話も若い人たちと進んでいます。
認知症カフェの活動は、わたしにとってもとても大事だし、これを続けることはわたしのライフワークだと思っているんですよ。
中島 珠子(なかじま たまこ)さん
1953年生まれ。看護師を勤めるが結婚を機に退職。その後、30年余のブランクを経て高
齢者デイサービスの看護師として復職した。一貫して、地域で暮らすこと、高齢者の課題、認知症の課題に目を向け、自宅を解放してのお茶会を在職中から開催。それが発展して、たんぽぽカフェ、café マリエなど、現在につながる活動となっている。体調を崩して 2019年に施設を退職した後も精力的に活動を広げ、コロナ禍の 2021年からは、仲間の看護師と一緒に「暮らしの保健室」を開所。多世代交流の場として活用しつつ、気楽な悩み相談の場を開いている。さらに、2025年1月からは、地域にこだわらない情報交換の場「結の碧空(ゆいのあおぞら)」もスタートさせた。

さまざまな世代の仲間が集う結の碧空の企画会議の様子。右手前が中島さん。
取材を終えて
社会の認知症への理解は進んできているとはいえ、まだまだ「なにもわかっていない人」という偏見は根強く、私自身も偏見は「まったくない」とはいえません。さらに若年性認知症においては、現役世代ということもあり、就業の継続の困難、子育ての困難、世帯の経済的困難など多くの生活課題に直面することもあらためて認識しました。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年を迎えた今年。認知症カフェは今後ますます地域に必要不可欠なものとして、存在価値を高めていくと感じました。
「ファンタスティック・プロデューサー」で、ノンフィクション作家の久田恵が立ち上げた企画・編集グループが、全国で取材を進めていきます
本サイト : 介護職に就いた私の理由(わけ)が一冊の本になりました。
花げし舎編著「人生100年時代の新しい介護哲学:介護を仕事にした100人の理由」現代書館