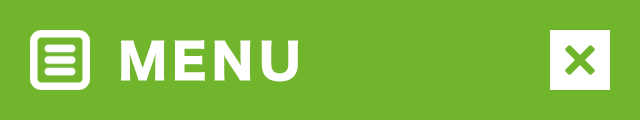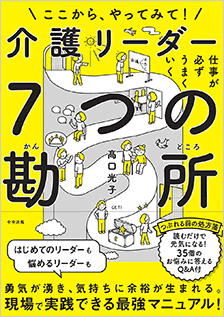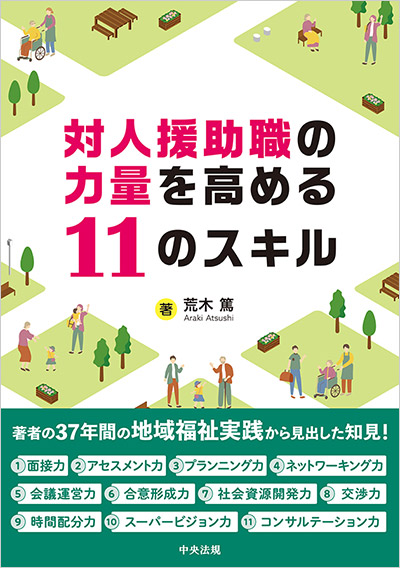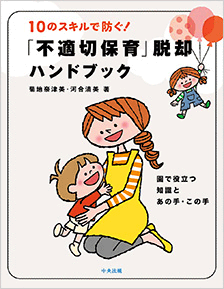死をことほぐ社会へ向けて
【第4回】
人生100年時代の死に場所
……長生きと家で死ぬことの矛盾

誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
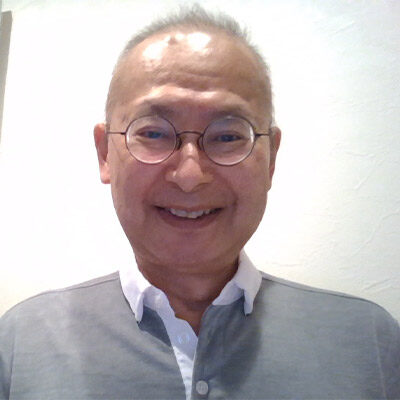
人生100年時代の落とし穴と矛盾
世の中では「人生100年時代」というキャッチコピーがやかましい。いきなりやかましいと書いたが、ここには介護・ケアの排除という視点がある。どういうことか。人生100年時代というキャッチコピーに伴うのは、「元気で100歳まで」、「健康寿命を伸ばそう」ということである。話題は医療の話ばかり。こうすれば若返られる。ああすればいつまでも歩ける。そんな話題とともに「人生100年時代」を目指そう。これを別の言い方にすると、「介護・ケアを必要としない人生100年」とも言える。
「100歳まで生きると介護・ケアが必要になるので、どういう介護・ケアを受けるか考えましょう」というのが現実的ではないかと思うが、そんな話はめったに聞かない。それが話題になるとしても、どこで死ぬかとか、どこまで医療を受けるかということばかりで、介護・ケアそのものが話題にならない。
現実には病院で死ぬ人が多いにもかかわらず、希望としては家で死にたいという人が多いという統計データがある。しかし、それは単なるアンケートの結果に過ぎない。
私が勤務する特別養護老人ホームでも、何割かの人は心臓マッサージやAEDの使用まで希望している。実際に心臓マッサージを行いながら病院に搬送することもある。家で死にたいというのは、回復の可能性があればできるだけ医療を受けたうえで、それでもだめなら家で死にたいということに過ぎないのではないかという気がする。人生100年を目指す社会の影響はここにもある。家で死にたいということを優先して医療を拒否すれば、人生100年は実現しがたい。
家で死にたいと希望する人が多いにもかかわらず病院で死ぬ人が多いというのは、家で死にたいのに死ねないということだけではなく、家で死にたいのはやまやまだけど、できるだけ長生きしたいので病院で死ぬのもやむ得ないということではないだろうか。家で死にたいという気持ちと長生きしたいという気持ちは相反する。社会は人生100年時代という中、家で死にたい、これはなかなかの難問である。
在宅、施設での介護・ケアの重要性
現実に訪問診療や施設で最期まで過ごしたいという人も、肺炎や尿路感染、心不全の悪化など急に具合が悪くなれば、入院を希望する場合が多い。その結果病院で亡くなるということもしばしばだ。施設で看取る方針がはっきりするのは、本人とのやり取りが困難になり、死がすぐそこまで迫っている状況になってからで、そうなってようやく家族との間で合意が取れるという場合が多い。それは本人の意思確認をしていないからでしょうという反論があるかもしれない。その反論についてはこの先の連載の中で別に論じたい。
家で死ぬということを、医療を受けるか受けないかという対立で考えると、医療を受けないということになるのだが、よほど死が近づいた状況にならなければ、医療を受けないという選択は困難だ。それは看取りを前提にした訪問診療や特養のような施設の現実にも表れている。そこには常にどのように介護・ケアを提供するかという問題があるのだが、それがないがしろにされている。入院すれば食事介助が受けられず、拘束されて点滴になりますとか、入浴はできませんとか、着替えを毎日行うことはできませんとか、トイレ誘導ができずおむつになりますとか、外出はできませんとか、介護・ケアの提供が困難になる。このまま家に居れば、あるいは施設に居れば、今のような介護・ケアを引き続き提供できるという大きな利点がある。そこがもう少し強調できれば、家で死にたいという希望に対して、医療との対立で行き詰ることも少なくなるのではないだろうか。