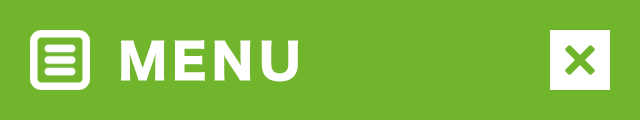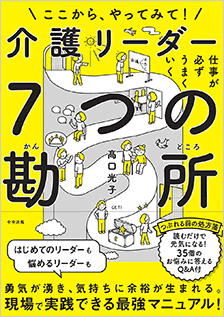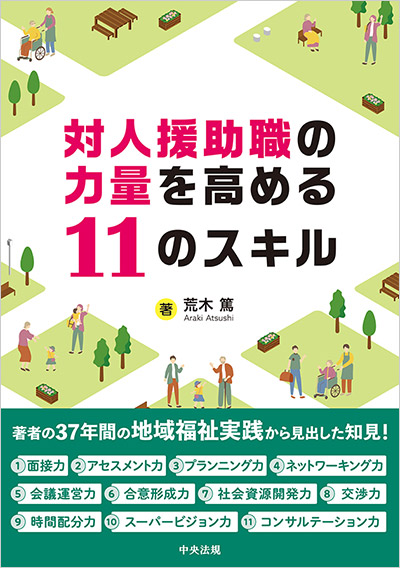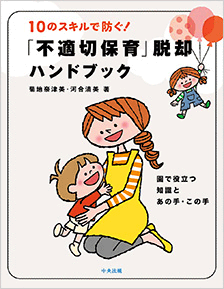死をことほぐ社会へ向けて
【第3回】
死ぬまでは生きている
……死のコントロールではなく日々の生活のコントロール
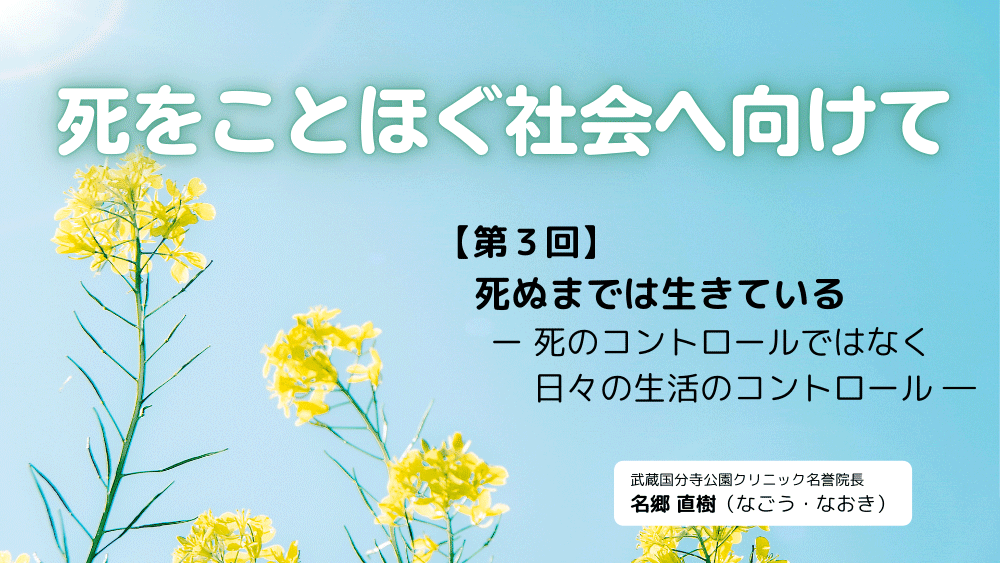
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
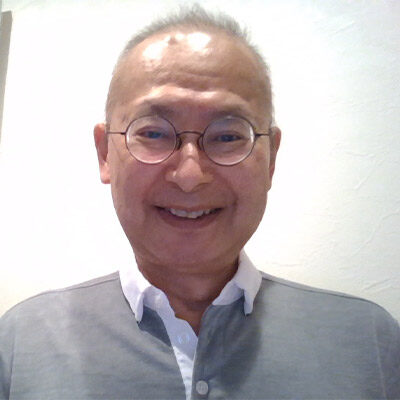
医療における未来志向
「死」は生きている間は、常に先のこととしてある。さらには先のことはわからない。ただそれは死に限ったことではない。「一瞬先は闇」というではないか。その先を予測し、そなえようというのは医療に限ったことではない。世の中全体が将来を予測し、それに対応することを是としている。というか、それこそが世の中の進歩といってもいいかもしれない。
その中の一つとして「死」もある。死に限らず一般的なこととして考えれば、現在は現実だが、未来は未定ということだ。その未定に対して、予測してそなえるのが現代だ。常に未来のことを考慮して今を生きる。この一般的なことを今一度、医療、介護・ケアに戻して考えてみる。
医療は現在も未来も考慮する。今の痛みをとるのは現在だ。降圧薬を処方する。ワクチンを接種する。これは未来の脳卒中や心疾患、感染症を予防するためだ。しかし、どうしても視点が未来に偏りがちになる。現在の痛みをとるのも、明日も元気でいられるようにという未来を向いている。医療においてこの未来志向はいまだに健在だ。よりよい未来の実現は、医療の進歩の原動力であり、進歩そのものでもある。ただ最終的に個人個人の死という限界が来る。死の向こうに未来はない。「もうできることはありません」ということになる。しかし、死ぬまでは生きている。
介護・ケアによる現在の生活の重視
この医療に対して介護・ケアはどうか。今の食事の準備や介助、今着ている服の着替え、今行きたいところへの外出介助、排泄の介助、すべて現在に視点がある。現在に視点を移せば、食事の介助も着替えも、外出も可能だ。現在に視点を置く限り、常に「できることがある」というのが、「もうできることはありません」という医療との決定的な違いだ。そして、現在に視点を置き、医療よりも介護・ケアを重視していくことが、死をコントロールしないですむ世の中につながっているのではないか。
しかし、介護・ケアにも未来の視点を軽視できない現状もある。例えば介護施設での入浴である。入浴前に血圧を測り、「血圧が高いので今日は入浴をやめておきましょう」というような場合だ。これは医療の王道である現在より未来の重視という立場が、介護・ケアにも大きな影響を与えているのだろう。もちろん個人個人では入浴中に死ぬのは嫌なので入浴しないというのも理解できる。しかし、風呂につかりながら死ぬなんていいじゃないか、病院で管につながれて死ぬより全然いいじゃないかという意見もある。
介護・ケアの場面で必要なのは、入浴を避けたい前者も許容しつつ、むしろ後者の今入浴したいという人を支援することではないか。さらに言えば、前者の人も医療の偏った未来志向に影響されているだけで、介護施設から、「入浴して具合が悪くなれば対応しますから、入ってもいいですよ」とか、「多くの人は入浴前に血圧なんか測ってませんから、気にせず入浴してはどうですか」とか言われたら、考えが変わるかもしれない。ぜひこんなふうに利用者に言ってみてほしい。案外多くの利用者の賛同が得られるのではないだろうか。私自身は介護施設から血圧が高いけど入浴させていいかという問い合わせが来た時に、「本人がいいと言えばぜひ入浴してもらってください。入浴後は血圧が下がっていることも多いですから」なんて答えている。明日の死より、今の生活を重視したいということである。さらにこの先の死のコントロールは困難だが、現在の生活のコントロールは容易である。
未来の死のコントロールではなく、現在の生活のコントロールこそ、介護・ケアの最も重要な部分だろう。「死んだらどうするんですか」ではなく、「死ぬまでお手伝いしますよ」というのが介護・ケアである。またしても釈迦に説法かもしれないが。