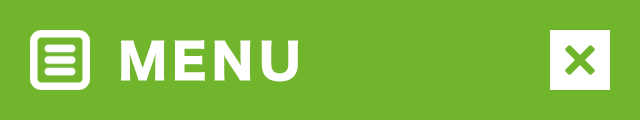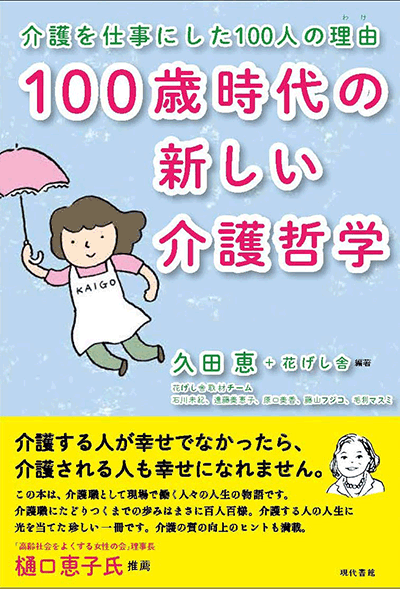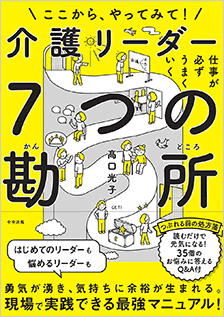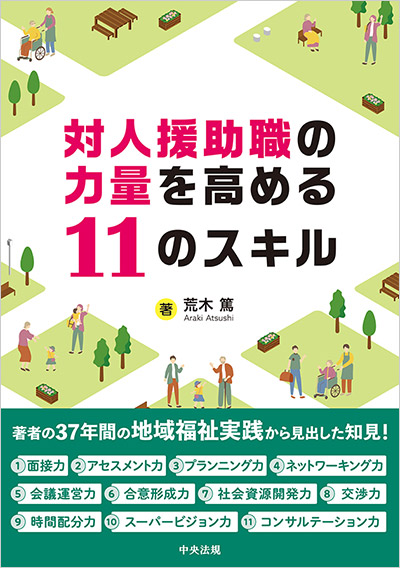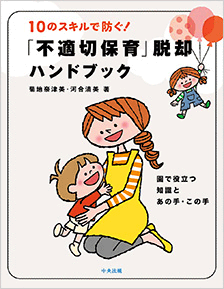福祉の現場で思いをカタチに
~私が起業した理由 ・トライした理由 ~
志をもってチャレンジを続ける方々を、毎月全4回にわたって紹介します!
Vol.79 連載第2回
言葉と同様、音楽も
コミュニケーションツールの一つ

後藤 聖子(ごとう しょうこ)
ヨーロッパでオペラ・オペレッタ・ミュージカル・コンサートなどの舞台活動ののち、音楽を自由に奏でる楽しさを分かち合いたい、きらきらと人生を輝かせる時間を作りたいと「シュピーレン」を設立。障がい児・者、高齢者等の福祉施設で音楽ワークショップファシリテーターとして活動。併せて、演奏、演出・コンサートの企画をおこなっている。2024年1月NPO法人を取得。音楽健康指導士。知的障がい者理解基礎講座、発達支援サポーター講座等修了。
取材・文 石川未紀
――前回は福祉施設で音楽を共に楽しむ「ファシリテータ―」となるまでのお話を伺いました。障がい者の生活介護施設で音楽を通じた活動を始められたのですね。
はい。言葉はツールですよね。音楽もツールだと思うんです。今、施設で私は手話を用い、身体を使って歌い表現する、ということを積極的におこなっています。バレエをやっていたので、それが感覚的にもしっくりきます。
手話で歌うきっかけはコロナ感染拡大のためでしたが、手話は聴覚障がい者だけでなく、他の方も、より笑顔が増えました。
また、聴覚に障がいがあるから音楽はできないとわけではありません。腕に指でピアノを弾くようにリズムをとるとニコニコしています。また、ピアノの下にもぐって振動を感じてもらうと、振動が伝わるたびにわくわくとした笑顔でいっぱいになります。
施設には自閉傾向の強い方もいて、生の音楽を聴くのは苦手という方もいます。その点、CDの音楽は当たり前ですが、毎回同じです。同じものが正しく来るというのは、とても安心するんですね。でも、生演奏は、例えばオペラでも、うわーと音を伸ばしてから、巻いて巻いて戻して着地をつくるということをします。毎回、同じ人が歌っても、生まれ出る音楽は微妙に異なります。
だからこそ、おもしろく、心を動かすのだと思います。
私は、シュピーレンの活動を始めたころは、障がいに対する予備知識がないので、好きなように音楽をやりました。ピアノも得意ではないので、時々間違える。そのたびに混乱するような方もいました。でも、今は平気です。彼らの眠っていた才能が目覚めて、鍛えられるんです。伸びしろはいっぱいある。私のピアノが下手くそで仕様がないと思っているのかもしれないけれども(笑)。童謡なども勝手にキーを変えて歌ったりするので、それも自閉傾向のある方にとっては戸惑いになる。けれど、気にせずにやっていると、彼らは両方聴けるようになっていくんです。その両方が「既存」になりバージョンが増えていくのだと思います。私はそこを目的としているわけではないのですが、結果として幅が広がっているのです。
私は元来知りたがり屋なので、知的障がい者理解基礎講座、発達支援サポーター、てんかん、失語症などのセミナーなど、さまざまな講座を受けています。私が大学時代にお世話になった先生に音楽療法についても伺いました。
ただ、知識が先に入り、先入観で「こうだからできない」とか「こういうふうにするとこんな成果がある」というような“指導”をするつもりはないんです。先のお世話になった先生も「音楽は喜びのためにある、音楽は神様がくれた贈り物」とおっしゃっていたのですが、私も心からそう感じています。
――そうした気持ちが相手にも伝わって、楽しいという気持ちにさせるのかもしれませんね。
ええ。そうかもしれませんね。
楽器は寄付していただいたり、自前で買ったりしたものを使用しているのですが、楽器はなるべく大切に扱ってほしい。活動する際も、自分たちで楽器を取りに行って、終わったら自分たちで片付けるということを大切にしたいと思っています。
ところが、終わりを告げると思い切り投げてしまう人もいましたし、楽しすぎて渾身の力で叩いて、太鼓が壊れてしまうこともありました。どうやったら楽器を大切に扱ってほしいということが伝わるかを考えました。言葉で、「そおっとに置いてください」「やさしく置いてください」と言ってもなかなか伝わりませんでした。
そこで、ふんわりとしたやわらかい布を持ってもらい、歌いながらふわふわと風になびかせてみたり、利用者の方の手のひらに乗せてみたりしました。そうやって楽しんだ後に、「布をゆっくりと置いてください」と伝えてみました。「早い」「ゆっくり」はわかりやすいようでした。
そして「そのふんわりとした布を置くように、ゆっくり楽器を置いてください」と、伝えるようにしました。もちろん、何回も何回も繰り返しましたが、少しずつゆっくりと置くようになっていきました。理論でこうしなければ、というよりは感覚として覚えていくのだと思います。試行錯誤を繰り返しながらですが、音楽を通じて伝え方もあれこれやってみる。それもまた、私にとってはとても楽しい時間です。
――ありがとうございました。次回はNPO法人を立ち上げる経緯を伺います。
第3回は3月17日(月)掲載
後藤聖子さん(ごとう しょうこ)さん
NPO法人シュピーレン理事長
フェリス女学院短期大学音楽科声楽専攻卒。同研究科修了(現フェリス女学院大学)。1989年オーストリア・ウィーンに渡欧。ウィーン・プライナー・コンセルヴァトリウムオペラ科及び演劇科で学び、オペラ科演出助手として主にモーツァルトのオペラ作品に関わる。その後ヨーロッパ各地の音楽祭やコンサートに出演。98年よりミュージカル「王様と私」にオリジナルキャストとしてヨーロッパ各地にて出演。2006年帰国後もウィーン、日本にてソロリサイタルや各種コンサートを開催。2015年より、生活介護事業所等にて音楽ワークショップ「シュピーレン」のファシリテーターとして活動。コンサートの企画・演奏・演出もおこなっている。2024年1月にNPO法人シュピーレンを設立。理事長に就任。音楽を通じて喜びを分かち合い、きらきらと人生を輝かせる時間を一緒につくる支援をめざして活動中。

心と身体で音を感じる
「ファンタスティック・プロデューサー」で、ノンフィクション作家の久田恵が立ち上げた企画・編集グループが、全国で取材を進めていきます
本サイト : 介護職に就いた私の理由(わけ)が一冊の本になりました。
花げし舎編著「人生100年時代の新しい介護哲学:介護を仕事にした100人の理由」現代書館