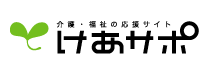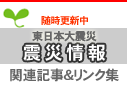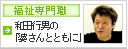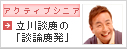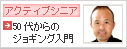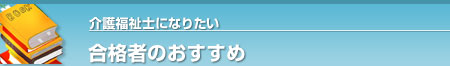
受験勉強も大事ですが、資格はなりたい自分に近づくための手段。合格後の「仕事のイメージ」を抱くことも大事です。このコーナーでは、資格の世界を知るのに役立った本や映画などを合格者が紹介します。

「わたし」の人生 〜我が命のタンゴ〜
監督・原案:和田秀樹
出演:秋吉久美子 橋爪功
配給:ファントム・フィルム
※8月11日(土)より、シネスイッチ銀座ほか、全国公開
「これからの介護との向き合い方」
精神科医の和田秀樹さんが監督・原案のこの映画は、父と娘の物語です。父と同じ大学教授の道に進もうとする百合子。英文学の名誉教授である父・修治郎。母親の死をきっかけに、父は暴力や痴漢行為で、警察に保護されることが続きます。病院での診断は「前頭側頭型認知症」。
介護の現場では、アルツハイマー型認知症や、前頭側頭型認知症と診断された利用者さんとかかわることは多いです。また、家族の心労をお聞きすることもあります。
ですが、何人、何十人というなかの“一人ひとり”の利用者さんとその家族が、こうやって葛藤や苦しみを抱え、ようやくサービスを使っているのだということをあらためて感じる作品でした。皆が「わたしの人生」を歩んでいる。その途中に「認知症」や「介護」が登場したのだと。
「家で親を介護することが最善」とされる傾向は、いまだに日本社会に根付いていると思います。介護が原因で仕事を辞める人の多くは女性です。ですが、介護される側とする側の距離感もさまざまで、いろんな形の介護があっていいのだと、考えさせられました。相手と向きあうところからスタートするアルゼンチン・タンゴが、物語に希望を与えてくれる存在になっていました。向きあうことの大事さ、難しさ―――。現場に出るときの気持ちが、また新たになったように思います。
前頭側頭型認知症という病気の存在や、一番近しい人が“攻撃”の対象となってしまうことなど、老年精神医学を専門とする和田さんが臨床で見てきた実際のエピソードを踏まえ、たくさんの人に知っておいてほしいと思っていることが散りばめられているようにも感じます。そういう意味では、家族介護者にもおすすめです。
ちなみに、劇中のように、利用者さんに愛され、育てられる若手男性職員がもっと増えればいいなと思います(笑)。
(デイサービス ビックス)