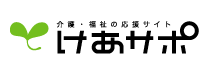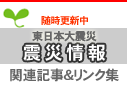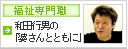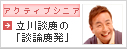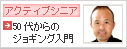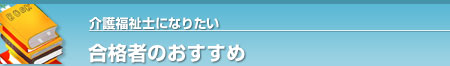
受験勉強も大事ですが、資格はなりたい自分に近づくための手段。合格後の「仕事のイメージ」を抱くことも大事です。このコーナーでは、資格の世界を知るのに役立った本や映画などを合格者が紹介します。

私は誰になっていくの? アルツハイマー病者からみた世界
クリスティーン・ボーデン=著、 桧垣陽子=訳
クリエイツかもがわ
ISBN:4-902244-10-1
価格:¥2,100(税込)
クリエイツかもがわ
ISBN:4-902244-10-1
価格:¥2,100(税込)
本人の声を聞く。そして私たちは何をするのか
この秋、オースラリアから本書の著者クリスティーン・ブライデンさんが来日されました。クリスティーンさんは、認知症をもつ人が自らの言葉で語り始める流れの端緒となった女性で、認知症を発症してから2冊の著書(『私は誰になっていくの?』『私は私になっていく』)を書き上げました。政府高官を務め、シングルマザーとして3人の娘をもっていた彼女は、46歳でアルツハイマー病と診断されました。本書では、認知症の人の体験世界――検査・診断のときの衝撃や恐怖、少しずつ失われていく機能への思い、世界がどのように見えるのか、周囲にどのような理解を求めているか――がクリスティーンさん自身の言葉で綴られています。理知的な文体で情緒豊かに、時にユーモラスに語られる彼女の思いにも、さまざまな葛藤や苦悩が現れます。
本書の中盤で触れられるのは、12歳の次女と8歳の三女が口論したエピソード。次女はそのときの母の態度が不公平だったこと、自分が孤立感を感じたことを手紙にしてクリスティーンさんに渡しました。
「私は明らかに彼女に間違ったことをしたとわかったが、母としての務めを果たすにはひどく疲れすぎていて、考えたり、話すことすら難しく、次のようなメモを書いて渡した。
頭に病気のある人を正常な人と同様に扱うのは公平ではないわ。(中略)私には、自分ではどうすることもできないの――頭に病気があるから――この『幸せなお母さん』の役を続けられない。私は幸せではないわ。ストレスを感じているし、あなたが私に我慢しなくてよいように、もう少し早く死ねたらよいのに。」
体験したことのない人間は、完全には理解することができない苦しみと過酷な状況が確かにそこにあることが、文章からたびたび伝わってきます。
何でもいっぺんに片づけてしまう「同時進行人間」だった彼女は、物事を1つずつやる習慣をつけ、そしてポールさんというパートナーを得ました。また、宗教という癒しも彼女の魂を強く支えました。
発症して17年目、5度目の来日となった今回、講演中の彼女の言葉のなかでひときわ強調されたのは「イネブラー(enabler)」でした。残された能力を最大限引き出し、その人らしく生きることを“可能”にしてくれるパートナーを指す、彼女独自の言葉です。「ポールは私のイネブラー。それはケアギバー(caregiver)よりも重要なことです」。

「認知症の人に学び、ともに歩むin東京」講演で(2012年10月28日)
現在、日本でも多くの認知症の人が自らの言葉で語り始めています。介護業界では古典とも言える本書ですが、認知症の人の言葉を聞くことの重要性を変わらず強烈に教えてくれます。介護者として、そこからの学びをどんなアクションにつなげていくのか――それを考えながら読み進めていただきたい一冊です。
(メソメソ)